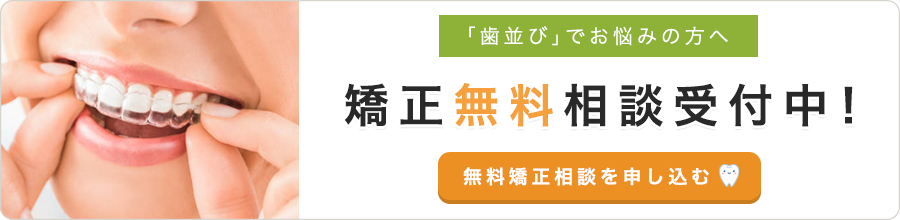こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
近年増えているお子さんのトラブルの一つに「口呼吸」があります。
「うちの子、いつも口が開いている」「寝ているときに口をポカンとしている」という相談を受けることが多くなりました。
実は口呼吸は単なる癖ではなく、歯並びや顎の発育、さらには全身の健康にまで悪影響を与えるのです。
今回は、口呼吸と歯並びの関係について詳しくご説明します。
目次
口呼吸とは?
通常、人間は鼻で呼吸するのが自然で健康的です。鼻呼吸には、空気の加湿・加温・異物除去など多くの役割があります。
しかし鼻が詰まっている、舌や唇の筋力が弱いなどの理由で、無意識のうちに口で呼吸してしまう状態を「口呼吸」と呼びます。
特に成長期のお子さんに口呼吸が続くと、歯並びや顎の発育に大きな影響を与えます。
なぜ口呼吸になるのか?
- 鼻詰まり・アレルギー性鼻炎:鼻が慢性的に詰まり、口で呼吸するしかなくなる。
- 扁桃腺やアデノイド肥大:喉の奥が塞がり、鼻呼吸がしにくい。
- 舌の筋力不足:舌が上顎に収まらず、口が閉じにくい。
- 口周りの筋力低下:唇を閉じる力が弱く、常に口が開いてしまう。
- 姿勢の悪さ:猫背やうつむき姿勢で下顎が下がり、口呼吸を誘発。
口呼吸が歯並びに与える影響
口呼吸が続くと、歯並びや顎の発育に次のような影響を及ぼします。
- 出っ歯(上顎前突):口が開いている時間が長いと、唇の圧力がかからず前歯が前に出やすくなる。
- 開咬:舌が下がるため上下の前歯が噛み合わず、前歯に隙間ができる。
- 叢生(ガタガタの歯並び):舌が正しい位置にないため上顎の横幅が狭くなり、歯が並びきらなくなる。
- 受け口:上顎の成長不足や下顎の突出につながる場合もある。
つまり、口呼吸は歯並びを乱す大きな原因の一つなのです。
放置するとどうなる?全身へのリスク
口呼吸は歯並びだけでなく、全身にも様々なリスクをもたらします。
- 虫歯・歯周病リスク増加:口が乾燥し、唾液の自浄作用が低下(予防歯科)。
- 口臭:乾燥により細菌が繁殖しやすくなる。
- 睡眠の質の低下:いびきや無呼吸につながる場合がある。
- 集中力の低下:脳への酸素供給が不足し、学習や運動に影響。
- 姿勢の悪化:猫背やストレートネックの原因にもなる。
自宅でできる口呼吸チェック
次の項目をチェックしてみましょう。複数当てはまれば口呼吸の可能性があります。
- 普段から口が開いている
- 寝ているときに口が開いている、いびきをかく
- 口を閉じると顎の下に梅干し状のシワができる
- 鼻で呼吸するのが苦しそう
- 前歯が出てきている気がする
改善のための方法
口呼吸を改善するには、原因を見極めた上で正しいアプローチを取る必要があります。
- 耳鼻科での診察:鼻づまりやアデノイド肥大がある場合は耳鼻科での治療が必要。
- 口腔機能トレーニング(MFT):舌や唇、頬の筋肉を鍛え、正しい舌の位置と鼻呼吸を習慣化。
- 小児矯正:顎の成長を利用しながら歯並びと呼吸の改善を行う(小児矯正)。
- 成人矯正:成長後でも歯並び改善による呼吸改善は可能(成人矯正(インビザライン))。
- 生活習慣の改善:姿勢を正す、就寝時の環境を整えるなど。
当院でのサポート
当院では小児歯科として、お子さんの口呼吸の早期発見と改善に取り組んでいます。
定期検診で歯並びや顎の成長をチェックし、必要に応じて予防歯科や小児矯正を組み合わせた治療を行います。
また、成人の方に対してはインビザラインによる目立たない矯正治療も対応しており、歯並びと呼吸機能を両立させるサポートを行っています。
まとめ
口呼吸は「癖だからそのうち治るだろう」と軽視されがちですが、歯並びや顎の成長に大きな悪影響を及ぼします。
放置すると虫歯・歯周病リスク増加や全身の健康問題にもつながります。
「安城 小児歯科」「新安城 小児矯正」で検索される保護者の方は、ぜひ早めの受診をおすすめします。
当院では、歯並びと健康な呼吸の両立を目指したサポートを行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長