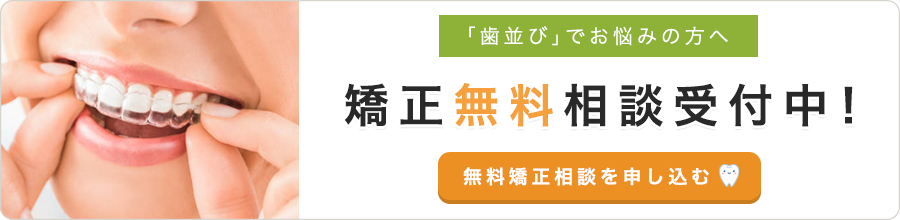こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
小さなお子さんによく見られる「指しゃぶり」。乳幼児期の成長過程で自然に見られる行動ですが、長期間続けると歯並びや顎の発育に悪影響を及ぼすことがあります。
今回は、指しゃぶりがどのように歯や顎に影響するのか、やめるタイミングや改善方法、そして当院での取り組みまで詳しく解説します。
目次
- なぜ子どもは指しゃぶりをするのか?
- 指しゃぶりが歯並びに与える影響
- 悪影響が起きるメカニズム
- 放置すると起こりうる将来のリスク
- やめるタイミングと年齢の目安
- 改善のための具体的なステップ
- 当院でのサポート体制
- まとめ
なぜ子どもは指しゃぶりをするのか?
指しゃぶりは、生まれたばかりの赤ちゃんが持つ「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」の延長です。
母乳やミルクを吸うことで安心感を得られるため、眠いときや不安なときに自然と指を口に入れてしまいます。
1〜2歳までは成長発達の一部として見られますが、3歳を過ぎても続く場合は注意が必要です。
この時期からは、顎や歯列の形成が本格的に進むため、外から加わる力が発育に大きく影響し始めます。
指しゃぶりが歯並びに与える影響
指しゃぶりは、指が口の中にあることで常に歯と顎に圧力をかけます。その結果、以下のような歯並びの異常が起こりやすくなります。
- 開咬(かいこう):上下の前歯が噛み合わず、前方に隙間ができる状態。
- 上顎前突(じょうがくぜんとつ):いわゆる出っ歯で、上の前歯が前方に傾く。
- 歯列弓の狭窄:上顎の横幅が狭くなり、歯列がV字型になる。
- 奥歯の噛み合わせのズレ:上下の歯列の位置関係が変わり、左右のバランスが崩れる。
悪影響が起きるメカニズム
歯や顎は、筋肉や舌、唇からの力のバランスで正しい位置を保っています。
指しゃぶりはこのバランスを崩す大きな要因の一つです。
- 指をくわえることで舌が下に押し下げられる。
- 舌が上顎に接していないため、上顎の横方向の成長が妨げられる。
- 唇の閉じる力が弱まり、口呼吸の習慣がつく。
- 結果として歯並びが乱れ、顎骨の形も変化する。
この変化は幼児期に始まり、小学生の間に固定化してしまうことも少なくありません。
放置すると起こりうる将来のリスク
- 矯正治療の長期化・高額化:ワイヤー矯正やインビザラインが必要になるケースが増えます。
- 発音障害:「さ行」や「た行」が発音しにくくなる。
- 口呼吸の慢性化:お口ポカンの状態が続き、虫歯や歯周病のリスク増加。
- 顔貌の変化:下顎が後退し、面長や受け口傾向になる。
これらは見た目だけでなく健康や心理面にも影響します。特に学童期以降は改善に時間がかかりやすくなります。
やめるタイミングと年齢の目安
指しゃぶりは3歳までにやめるのが理想です。4歳以降は顎骨への影響が顕著になり、6歳を過ぎると恒常的な歯列不正の原因になります。
卒乳後も指しゃぶりが続く場合は、早めに専門医に相談しましょう。
改善のための具体的なステップ
- 心理的サポート:叱らず、安心できる代替行動を与える。
- 生活習慣の見直し:就寝前のルーティンを作り、指を口に入れる機会を減らす。
- 口腔機能トレーニング(MFT):舌の位置や口輪筋を鍛える(小児矯正ページ参照)。
- 装置療法:必要に応じて、口の中に指を入れにくくする矯正装置を装着。
特にMFTは、再発防止にも効果的で、口呼吸や舌癖の改善にもつながります。
当院でのサポート体制
当院は小児歯科として、指しゃぶりの早期発見・改善に力を入れています。
予防歯科の観点から、悪習癖の改善は虫歯や歯周病の予防にもつながります。
保護者の方には、家庭での声かけ方法や環境整備のポイントもアドバイスしています。
まとめ
指しゃぶりは自然な成長の一部ですが、長期化すると歯並びや顎の成長に悪影響を及ぼします。
「安城 小児歯科」「新安城 小児矯正」で専門的に診てもらうことで、早期に対応でき、将来的な矯正負担を軽減できます。
気になる場合は早めのご相談をおすすめします。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長