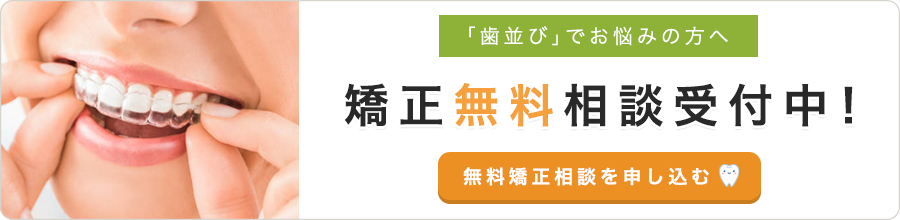こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
今回は、「被せ物を装着した後の歯がしみるのはなぜ?第二象牙質と神経の関係を徹底解説!」についてお話をしていきます。
歯の治療をした直後や、被せ物・詰め物を入れた後に「まだ歯がしみる…」「むし歯が残っているのではないか?」と不安になる方は少なくありません。その原因のひとつに、歯の内部で新しく作られる「第二象牙質」が深く関わっていることをご存じでしょうか。第二象牙質の働きや、治療後のしみる症状が起こる理由、対処法などを理解しておくことで、治療後の不安を和らげることができます。
本記事では、治療後に歯がしみるメカニズムと第二象牙質について、歯科医師の視点からわかりやすく解説していきます。歯の神経に負担がかかっている場合の対策や、金属の被せ物特有のリスクなども含め、幅広く取り上げますので、ぜひ参考にしてみてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【目次】
- 治療後に歯がしみるとは?
- なぜむし歯治療でしみやすくなるのか
- 第二象牙質ってなに?
- 第二象牙質が作られるまでの期間
- 金属の被せ物としみる症状の関係
- しみるときに考えられるその他の要因
- しみるときの対処法と歯科医院へ相談のタイミング
- まとめ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1. 治療後に歯がしみるとは?】
歯科医院でむし歯を削り、詰め物や被せ物を装着した後に生じる「しみる」症状は、冷たい水や空気に触れたとき、あるいは熱い飲み物を口に含んだときなどに起こりやすいものです。しみる感覚が軽度であり、時間が経つにつれて徐々に治まるようであれば、基本的には深刻な問題でないケースが多いです。しかし、「長期間にわたってしみる症状が強い」「痛みを伴って日常生活にも支障をきたす」などの場合は、神経にまで深刻なダメージが及んでいる可能性があるため、早めに歯科医院へ相談する必要があります。
【2. なぜむし歯治療でしみやすくなるのか】
むし歯を削る際は、むし歯菌が入り込んだ部分をしっかりと除去します。むし歯を残してしまうと再発リスクが高くなるので、必要な範囲を十分に削らなければなりません。ただし、削る量が増えるほど、歯の内部にある神経(歯髄)に近づいてしまいます。
歯には「エナメル質」や「象牙質」といった組織が存在しますが、象牙質の下には神経が通っています。削る範囲が深くなり、神経に近くなると、外部からの刺激(冷温刺激、化学的刺激、噛む力など)がダイレクトに神経へ伝わりやすくなり、しみる症状が出やすくなるのです。
また、神経に近い部分はデリケートであるため、強い刺激が繰り返し加わることで神経が弱ってしまうこともあります。その結果、「痛み」「しみる感覚」がより強く出る場合もあります。
【3. 第二象牙質ってなに?】
歯の神経が活力を保っている場合、歯は自分自身を守ろうとする働きを持っています。その代表が「第二象牙質」という組織です。
通常、歯は外側からエナメル質、その内側に第一象牙質(一般的に“象牙質”と呼ばれる部分)、さらに奥に歯の神経(歯髄)が存在しています。神経が刺激を受けると防御反応として、神経付近に新たな象牙質を作り出し、神経を保護しようとします。この新たに形成される層が「第二象牙質」です。
第二象牙質が十分に形成されると、外からの刺激が神経に伝わりにくくなるため、しみる症状が徐々に緩和されます。治療後、多少しみる感覚が残っていても、神経が元気な状態であれば、この第二象牙質が歯を徐々に守る形になり、やがて自然にしみにくくなることが多いです。
【4. 第二象牙質が作られるまでの期間】
第二象牙質が作られるスピードは人それぞれで、個人差が大きいのが特徴です。数週間でしみなくなる方もいれば、数か月から1年ほど経過してようやく落ち着く方もいます。
歯の神経がしっかりと生きている場合、時間とともに歯が自ら回復力を発揮し、しみる症状が徐々に改善していくことが期待できます。一方、神経のダメージが大きかった場合や、痛みが長期間続いてしまうようなケースでは、根管治療(神経の治療)が必要になる可能性もあります。
一般的には、治療後から半年ほどで「しみる感じがだいぶ軽減した」というケースが多いですが、その間に症状が強く出る場合は、我慢せずに歯科医院に相談することをおすすめします。
【5. 金属の被せ物としみる症状の関係】
被せ物の素材によっても、しみる症状の感じ方は異なります。特に金属の被せ物は、熱を伝えやすい性質を持っているため、冷たい食べ物や飲み物の刺激が歯の神経に伝わりやすく、結果的にしみる症状が強く出ることがあります。
一方で、セラミックやレジン(樹脂)など、金属ほど熱伝導率が高くない素材を使用すると、しみる症状が多少軽減されるケースもあります。ただし、素材によっては強度や磨耗性などの面で金属よりも劣る場合がありますので、歯科医師としっかり相談しながらベストな方法を選択することが大切です。
【6. しみるときに考えられるその他の要因】
(1) 歯ぎしりや食いしばり
歯ぎしりや食いしばりの習慣があると、治療した歯だけでなく周囲の歯にも大きな力がかかり、歯がしみるリスクが高くなります。噛み合わせのバランスが乱れると、治療部位に過度な負担がかかり、痛みやしみが長引くこともあります。
(2) 歯周病の進行
歯周病が進むと歯肉が下がり、歯の根元部分が露出することがあります。この部分は象牙質がむき出しになりやすく、敏感なため、冷たい刺激が伝わりやすくなってしみを生じることもあります。
(3) むし歯の再発や新たなむし歯
「しみる=むし歯が残っている」と決めつけられないものの、まれに治療後に別の部位でむし歯が発生し、しみる症状を感じることもあります。しみ方が強かったり、持続的な痛みがあったりする場合は、早めに検査を受けることが重要です。
【7. しみるときの対処法と歯科医院へ相談のタイミング】
(1) 治療後はしばらく様子を見る
前述のとおり、第二象牙質が作られるまでにある程度の時間を要します。数日から数週間程度は様子を見ながら、しみる状況が徐々に改善するかどうか観察しましょう。
(2) 適切なケアを継続する
歯磨き方法やフッ素入りの歯磨き粉を使用するなど、日常のセルフケアをきちんと行うことが大切です。歯ぎしりの傾向がある方は、ナイトガードを検討するのも良い方法です。
(3) 強い痛みやしみが続く場合は受診を
時間が経ってもしみる症状が変わらない、あるいは痛みや腫れがひどくなってくるといった場合は、神経が限界まで弱っている可能性があります。早めに受診して、根管治療など適切な処置を受けましょう。
(4) 金属が原因の場合の相談
金属の被せ物による熱伝導の問題が疑われる場合、セラミックなど他の素材に置き換える選択肢もあります。見た目の面でも金属アレルギーの面でもメリットが得られるケースがありますので、興味があれば歯科医師に相談してみてください。

【8. まとめ】
被せ物や詰め物を装着した後の「しみる」症状は、必ずしも治療の失敗やむし歯の残存を意味するわけではありません。削ったことで神経に近くなり、まだ第二象牙質が十分に形成されていないため、刺激が伝わりやすくなっている可能性が高いからです。第二象牙質は時間経過とともに作られ、外部の刺激から歯の神経を守ってくれる役割を担います。
ただし、いつまでも症状が改善しなかったり、痛みが増してきたりするような場合は、早めに歯科医院を再受診し、根管治療の必要性や被せ物の再調整などを含めた検査を受けることが重要です。
歯がしみるという小さなサインを見逃さず、適切なケアを続けていくことで、大切な歯を長期的に守ることができます。少しでも気になる症状がある方は、遠慮なく歯科医院にご相談ください。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長