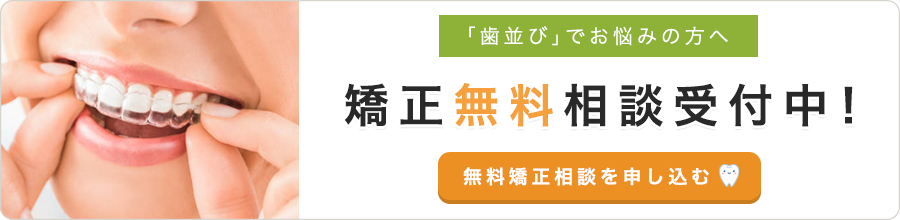こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
今回は、「歯磨き粉の正しい使い方と年齢別の適切な使用量」についてお話をしていきます。
歯磨き粉は、歯の表面をきれいにし、むし歯や歯周病を予防するための重要なアイテムです。しかし、「どれくらいの量を使ったらいいの?」「子どもの場合はどうすればいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実は、年齢や口腔内の状態に合わせた適切な量と使い方を守ることで、より効率的に歯を守ることができます。
本ブログでは、年齢別におすすめの歯磨き粉の使用量やそのメリット、正しいブラッシングのポイントなどをわかりやすく解説していきます。
──────────────────────────────────
【目次】
- 歯磨き粉の役割とは?
- 年齢別の歯磨き粉使用量 2-1. 6か月〜2歳 2-2. 3〜5歳 2-3. 6〜14歳 2-4. 15歳以上
- 使用量を守らないとどうなるの?
- 歯磨き粉選びのポイント
- 当院での取り組み:0歳からの健診の大切さ
- 正しい歯磨き習慣を身につけるために
- まとめ
──────────────────────────────────
【1. 歯磨き粉の役割とは?】
歯磨き粉には、主に以下のような役割があります。
- 歯垢(プラーク)の除去をサポートする
歯ブラシだけでも歯垢は落とせますが、歯磨き粉の発泡作用や研磨剤が加わることで、よりスムーズに歯面を清掃しやすくなります。 - フッ素などの予防効果
フッ素には、歯の表面のエナメル質を強化し、むし歯になりにくくする働きがあります。特に成長期のお子さまや成人でも、フッ素が含まれた歯磨き粉を使用することでむし歯予防が期待できます。 - 口臭予防や爽快感
歯磨き粉の清涼成分によって口臭が抑えられ、磨いた後の爽快感を得ることができます。
とはいえ、歯磨き粉の役割を十分に活かすためには、“適切な量”を使うことが大切です。次からは年齢別の目安量について見ていきましょう。
【2. 年齢別の歯磨き粉使用量】
年齢によって口の中の環境や歯列の状態は大きく異なります。そのため、歯磨き粉の使用量は以下のように工夫することをおすすめします。
6か月〜2歳
- 切った爪程度の少量、または使用しなくてもOK
生後6か月頃から赤ちゃんに歯が生えてきますが、歯磨き粉を使うと誤って飲み込んでしまうリスクが高いこともあります。そのため、歯ブラシを使う場合は「爪の先ほどの少量」もしくは「使わない」という選択肢も十分ありです。 - 前歯だけの場合はガーゼで拭き取りも◎
歯が数本しか生えていない場合や、ブラッシングになかなか慣れないうちは、柔らかいガーゼやウエットティッシュで歯の表面を軽く拭いてあげるだけでもOKです。むし歯予防だけでなく、赤ちゃんが口に異物を入れることに慣れ、歯磨きに対する抵抗を少なくするというメリットもあります。
3〜5歳
- 歯ブラシの先から約5mm程度
この頃からは乳歯もだいぶ生え揃い、奥歯(臼歯)も出てきます。歯磨き粉を5mm程度つけてあげると、フッ素の効果や研磨による歯垢除去を十分に期待できます。 - 噛み合わせの溝もしっかり磨く
乳歯の奥歯は噛み合わせが複雑になりがちで、溝に汚れがたまりやすいです。歯磨き粉をつけることでブラッシングがスムーズになりますが、泡立ちすぎに注意しながら、しっかりと磨き残しのないようにしましょう。
6〜14歳
- 歯ブラシの先から約1cm程度
6歳頃からは永久歯が生え始め、14歳前後まで徐々に子どもの口の中は乳歯と永久歯が混在した状態になります。生えたての永久歯はエナメル質がまだ弱いため、むし歯のリスクが高い時期でもあります。フッ素配合の歯磨き粉を1cmほどつけて、丁寧に磨くことが大切です。 - 生えかけの永久歯は要注意
とくに6歳臼歯や前歯が生え変わるタイミングでは、歯ぐきが腫れたりデリケートになったりすることがあります。そこで、あまり泡を立てすぎず、磨く時間は十分に確保してください。
15歳以上
- 1〜2cm程度(意外と多くつけなくてもOK)
大人の場合は1~2cmほどを目安にすると良いでしょう。歯磨き粉をつけすぎると、泡がたくさん立ってしまって「磨けている気分」になる一方、実際にはしっかり磨けていないケースも少なくありません。適量を意識して、口内のすみずみまできちんとブラッシングすることが重要です。
【3. 使用量を守らないとどうなるの?】
- 泡立ちすぎによる磨き残し
歯磨き粉をつけすぎると、泡が大量に出て視覚的に磨いている実感を得やすくなります。しかし、泡があると歯の表面を確認しにくく、結果的に磨き残しが出やすくなる恐れがあります。 - 歯磨き粉の無駄遣い
過剰に歯磨き粉を使用すると、当然ながら無駄も増えます。経済的な面だけでなく、環境への配慮も含めて適量を守ることが大切です。 - 効果が薄れるリスク
逆に少なすぎる場合は、フッ素や研磨効果が十分に得られず、むし歯予防効果が薄れてしまいます。せっかく歯磨き粉を使うなら、そのメリットを最大限に生かしたいですよね。
【4. 歯磨き粉選びのポイント】
- フッ素濃度を確認する
日本の市販品ではフッ素濃度はおおむね1000ppm前後ですが、高濃度フッ素配合(1450ppm程度)のものもあります。お子さまの場合は年齢に応じて低濃度のフッ素配合を選ぶなど、歯科医師や歯科衛生士と相談して決めるのがおすすめです。 - 研磨剤の種類や刺激の強さに注意
研磨剤の粒子が大きいものや、刺激の強い歯磨き粉は、歯や歯ぐきにダメージを与えやすい場合があります。歯質が弱い方や知覚過敏がある方などは、低研磨タイプを選択するのも一案です。 - 好みの味・香り
歯磨き粉の味や香りが合わないと、使い続けるのが苦痛になる方もいます。とくに小さなお子さまは「味が嫌だから歯磨きしたくない」と感じてしまうことがあるので、フルーツ系や優しいミント味など、好みに合わせて選ぶとよいでしょう。
【5. 当院での取り組み:0歳からの健診の大切さ】
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科では、0歳から健診を行っています。歯が生え始めてから歯磨き粉をどう使うか、そして成長段階に合わせたブラッシングの方法は、お子さまの口腔ケアを確立するうえで非常に重要です。
- 歯磨きに慣れるためのアドバイス
お子さまが小さいうちは、まずは「口の中に何かが入ること」に慣れてもらうことが大切です。歯ブラシやガーゼを使い、遊び感覚で口腔ケアをスタートしていただく指導を行っています。 - 一人ひとりに合わせた指導
当院では、月齢や年齢に応じて最適な歯磨き粉の使い方・仕上げ磨きの方法などをお伝えしています。赤ちゃんから小学生、中高生、そして成人の方まで幅広い年代にわたってサポートしています。
【6. 正しい歯磨き習慣を身につけるために】
- 1日2~3回のブラッシングを意識
朝起きたあと、昼食後、就寝前など、生活リズムに合わせてブラッシングのタイミングを作ることで、むし歯や歯周病を予防しやすくなります。 - フロスや歯間ブラシとの併用もおすすめ
歯と歯の間は歯ブラシだけでは磨ききれない部分が多いため、歯間清掃用具の活用も推奨しています。歯磨き粉を適量使いつつ、フロスや歯間ブラシで仕上げをすると効果的です。 - 定期的な歯科検診でプロのアドバイスを受ける
歯磨きのクセや磨き残しのチェックは、自分自身では見落としがちです。定期検診で歯科医師・歯科衛生士にチェックしてもらいましょう。

【7. まとめ】
歯磨き粉は「つければつけるほど良い」というわけではありません。年齢や口の状態に合わせて適切な量と使い方を守ることで、むし歯や歯周病を効果的に予防し、歯の健康を維持しやすくなります。とくにお子さまは乳歯から永久歯へと移行する大切な時期なので、正しい習慣を小さい頃から身につけられるよう、ぜひご家族で意識してみてください。
歯磨き粉の使い方で不安や疑問があれば、当院ではプロによるアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。一人ひとりのお口の状態に合わせたブラッシング指導や、フッ素の適切な使い方など、トータルでサポートいたします。毎日のケアをより効果的に、そして快適に行うためにも、ぜひ当院の定期健診をご利用ください。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長