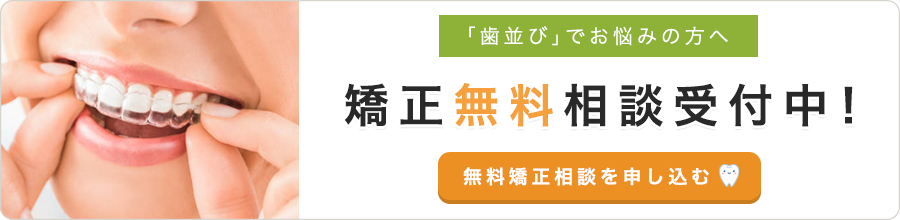こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
お子さんが寝ているときに「ギリギリ」と歯ぎしりをしている音を聞いたことはありませんか?
実は子どもの歯ぎしりは珍しいことではなく、多くの場合は成長の過程で一時的に起こる自然な現象です。
しかし中には、ストレスや心の負担が原因で歯ぎしりが起こるケースもあり、放置すると歯並びや顎に悪影響を及ぼすこともあります。
今回は「お子さんの歯ぎしりとストレスの関係」について詳しくお話しします。
目次
子どもの歯ぎしりとは?
歯ぎしり(ブラキシズム)とは、睡眠中や無意識のうちに歯を強くこすり合わせる行為です。
子どもの歯ぎしりは、乳歯が生えそろう3〜6歳頃や、永久歯に生え変わる6〜12歳頃に多く見られます。
成長の一環として一時的に起こる場合も多く、必ずしも心配する必要はありません。
ただし、長期間続く場合や歯の摩耗が進んでいる場合には、注意が必要です。
定期的な小児歯科でのチェックによって、歯の状態や噛み合わせを確認し、必要に応じて対策を行うことが大切です。

歯ぎしりとストレスの関係
子どもの歯ぎしりの原因は一つではありませんが、近年注目されているのが「ストレスとの関係」です。
環境の変化や心理的な緊張が、無意識のうちに歯ぎしりとして現れることがあります。
例えば次のような場面が考えられます。
- 幼稚園や学校など、生活環境の変化
- 家族間の緊張や兄弟関係の変化
- 習い事や学習によるプレッシャー
- 新しい経験や人間関係への不安
こうした心理的なストレスは、日中は意識していなくても、寝ている間に「歯を食いしばる」「こすり合わせる」という形で体に表れることがあります。
これは大人のストレス性歯ぎしりと同様のメカニズムです。
ストレスを原因とする歯ぎしりは、心と体のバランスを崩しているサインでもあります。
心の負担を減らすとともに、予防歯科で定期的にチェックを受けることが効果的です。
放置するとどうなる?歯や顎への影響
歯ぎしりを放置すると、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 歯の摩耗:乳歯がすり減り、冷たいものがしみたり、虫歯になりやすくなります。
→ 定期的な虫歯治療やフッ素塗布で予防しましょう。 - 顎関節への負担:強い歯ぎしりは顎に過度な力をかけ、顎の関節や筋肉の痛みを引き起こすこともあります。
- 歯並びへの影響:長期的な力が加わることで歯の位置がズレ、将来的な矯正治療が必要になる場合もあります。
→ こうした場合は小児矯正で顎のバランスを整えることが有効です。
家庭で気づくサイン
お子さんが歯ぎしりをしているかどうかは、次のようなサインで気づけることがあります。
- 寝ているときにギリギリという音が聞こえる
- 朝起きたときに顎が疲れた様子がある
- 歯の先が平らにすり減っている
- 歯ぐきが赤く腫れている、出血している
これらのサインが見られる場合は、小児歯科で相談し、原因を明らかにして適切な対応を行いましょう。
歯ぎしりを減らすための対策
歯ぎしりが続く場合は、以下のような方法で改善を図ります。
- 心理的サポート:安心できる環境づくりや、ストレスの原因を取り除くことが第一歩です。
- マウスピースの装着:歯の摩耗を防ぐために、夜間にマウスピースを使用することがあります。
- 噛み合わせのチェック:歯の高さや位置のバランスが悪い場合は調整を行います。
→ 歯周病治療や咬合治療も必要に応じて併用します。 - 成長を利用した矯正治療:歯並びや顎の成長に関わる場合は、小児矯正で根本的な改善を行います。
また、成人期に歯ぎしりが続く場合には、インビザライン矯正などで噛み合わせを整えることも効果的です。
当院でのサポート体制
当院では、歯ぎしりの原因を「歯」「顎」「心身」の3つの視点から分析し、包括的に対応しています。
– 成長期の歯ぎしりを見守る小児歯科診療
– 顎の発育を整える小児矯正
– 噛み合わせや筋肉バランスを考慮した予防歯科
– 歯の摩耗を防ぐための虫歯治療とインプラント治療への連携
こうした体制で、お子さんの成長段階に応じた最適なケアを行っています。
まとめ
お子さんの歯ぎしりは一時的なことも多いですが、ストレスや噛み合わせの問題が原因の場合もあります。
「安城 小児歯科」「新安城 小児矯正」でお探しの保護者の方は、ぜひ早めにご相談ください。
私たちは、歯だけでなく心のケアも大切にしながら、お子さんの健やかな成長をサポートいたします。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長