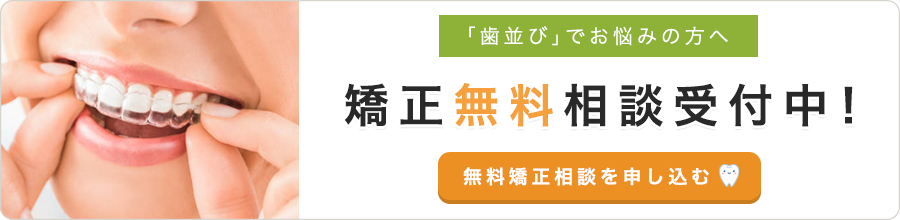こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
「歯並びが悪くなるのは遺伝だから仕方ない」と思われる方も多いですが、実は日常の“クセ”が大きく影響していることをご存じでしょうか。
特にお子さんの場合、口呼吸・頬杖・指しゃぶりなどの癖が続くと、顎や歯列の発育に悪影響を与えることがあります。
今回は、歯並びを悪くする代表的な習慣とその対処法について、わかりやすく解説します。
目次
なぜ生活習慣で歯並びが悪くなるのか
歯並びは「歯の大きさ」「顎の大きさ」「舌や唇など口まわりの筋肉のバランス」によって形成されます。
そのため、毎日の生活習慣や癖が長期間続くと、歯や顎の位置に微妙な力がかかり、少しずつ歯列が変化していくのです。
歯並びの乱れは見た目だけでなく、噛み合わせや発音、さらには呼吸や姿勢にも影響を及ぼすことがあります。
こうした原因を早期に見つけて改善するためには、小児歯科や小児矯正での定期的なチェックが大切です。
口呼吸がもたらす影響
鼻ではなく口で呼吸をする「口呼吸」は、歯並びや顔の形に大きな影響を与える代表的な悪習慣です。
本来、鼻呼吸をしていると舌は上あごにぴったりと付いていますが、口呼吸になると舌が下がり、上あごが狭くなりやすくなります。
結果として、出っ歯や開咬(前歯が閉じない状態)などの不正咬合を引き起こすことがあります。
また、口呼吸は口内が乾燥しやすく、虫歯治療や歯周病治療が必要になるリスクを高めます。
お子さんがいつも口を開けていたり、いびきをかいて寝ている場合は注意が必要です。
指しゃぶりが続くとどうなる?
赤ちゃんの頃の指しゃぶりは自然な行動ですが、3〜4歳を過ぎても続く場合は歯並びに影響を及ぼすことがあります。
指をくわえることで、前歯や上あごに力がかかり、前歯が前方に傾いたり、上下の歯が閉じなくなる「開咬」になることがあります。
また、長期的な指しゃぶりは舌の位置や噛み合わせにも影響し、発音がしにくくなることもあります。
このような場合、小児矯正によって顎の発育をサポートし、歯列を整えることで改善が可能です。
ご家庭では、「指しゃぶりをやめようね」と無理に叱るのではなく、安心できる環境づくりや代替行動を促すことが大切です。

頬杖・うつ伏せ寝の悪影響
頬杖をつく、あるいはうつ伏せで寝るといった習慣も、歯並びを歪ませる原因になります。
これらの姿勢では、常に片側の顎や歯に圧力がかかるため、骨の成長バランスが崩れ、顔の左右差が生じることがあります。
また、下あごが押し込まれることで受け口(反対咬合)になるリスクもあります。
成長期の顎はまだ柔らかく、わずかな力でも形に影響が出やすいため、寝姿勢や座り方の習慣にも気を配りましょう。
必要に応じて、予防歯科で噛み合わせチェックを行い、早期発見・早期対応を心がけてください。
今からできる改善方法
歯並びを悪くする習慣は、気づいた時点で改善を始めることができます。
次のようなステップを意識してみましょう。
- 鼻呼吸のトレーニングを行う(鼻づまりの解消・姿勢の改善)
- 頬杖をしないように意識する(机の高さや椅子の位置を調整)
- 指しゃぶりを卒業するための「ごほうびカレンダー」を導入する
- 噛む力を育てる食事習慣(硬い食材をよく噛む)を意識する
- 定期的に小児歯科でチェックを受ける
こうした取り組みを早期に行うことで、将来的に成人矯正(インビザライン)が必要になるリスクを減らすこともできます。
当院でのサポート体制
当院では、お子さんの生活習慣を踏まえたうえで、口腔機能や顎の成長を総合的に診ています。
– 成長段階に合わせた小児歯科診療
– 顎の発育を整える小児矯正
– 正しい噛み合わせを維持する予防歯科
– 永久歯期以降に対応するインビザライン矯正
– 噛む力の維持を目的としたインプラント治療
こうした多角的な視点で、お子さんの「これからの歯並び」を守ります。
まとめ
歯並びの乱れは、遺伝だけでなく日常のちょっとした癖によっても引き起こされます。
口呼吸・指しゃぶり・頬杖といった習慣を早めに見直すことで、将来の歯並びや顎の発育を健全に保つことができます。
「安城 小児歯科」「新安城 小児矯正」でお探しの保護者の方は、ぜひ一度当院にご相談ください。
お子さんの成長に寄り添いながら、美しい歯並びと健やかな笑顔を一緒に育てていきましょう。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長