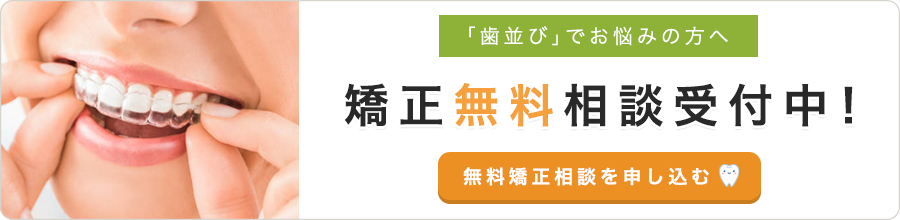こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
食事のときに「よく噛んで食べましょう」と言われたことは誰でもあると思います。
実は「噛む力」は歯や顎だけでなく、全身の健康にまで深く関係しています。
今回は、噛む力がどのように健康に影響するのか、そして歯科でできるサポートについて詳しく解説します。
目次
噛む力とは?
「噛む力」とは、食べ物をすりつぶし、飲み込むために必要な咀嚼機能のことです。
この力は歯や顎の骨、咬筋や舌の動き、そして正しい噛み合わせによって支えられています。
歯を失ったり、歯並びが乱れていたりすると噛む力が低下し、食事の満足度や健康状態に直結します。
噛む力が全身に与える良い影響
噛むことには「ひみこのはがいーぜ」という標語があるように、多くのメリットがあります。
- 肥満防止:よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べすぎを防ぐ。
- 味覚の発達:噛む回数が増えると、食べ物の味をしっかり感じられる。
- 脳の活性化:噛む刺激が脳の血流を増やし、集中力や記憶力の向上につながる。
- 消化を助ける:噛むことで食べ物が細かくなり、胃腸への負担が減る。
- 姿勢改善:噛み合わせが安定すると、頭や首のバランスが整いやすい。
このように、噛むことは単なる食事動作ではなく、健康な体づくりに欠かせない機能なのです。
噛む力が弱いと起こる問題
噛む力が低下すると、次のようなトラブルが出てきます。
- 消化不良:食べ物を細かくできず、胃腸に負担がかかる。
- 虫歯や歯周病のリスク増加:噛む回数が少ないと唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなる。
→ 定期的な予防歯科での管理が大切です。 - 発音障害:歯の本数が少ないと「さ行」「た行」が発音しにくくなる。
- 認知症リスクの上昇:研究では、噛む力の低下が脳機能の低下に関与する可能性が指摘されています。
子どもの噛む力と発達
子どもの噛む力は、顎の発育や歯並びにも直結します。
やわらかい食べ物ばかり食べていると顎の成長が不十分になり、歯がきれいに並ぶスペースが足りなくなります。
その結果、叢生(ガタガタの歯並び)や出っ歯、受け口などの不正咬合につながります。
このようなケースでは小児矯正が有効です。
また、乳歯の虫歯が多いと噛む力が弱まり、永久歯の正常な生え変わりにも影響するため、虫歯治療も欠かせません。
噛む力を守るためにできること
噛む力を維持・向上させるには、以下の取り組みが大切です。
- 虫歯や歯周病の予防:歯を失う最大の原因は虫歯と歯周病です。
定期的に歯周病治療や予防歯科を受けましょう。 - 正しい歯並びを整える:噛み合わせを良くすることで効率的に噛めるようになります。
→ 成人矯正(インビザライン)や小児矯正が役立ちます。 - 失った歯の補綴:歯を失った場合は放置せず、インプラントなどで補うことが重要です。
- 食生活の見直し:噛み応えのある食材(野菜・海藻・ナッツ類など)を取り入れる。
- 口腔機能トレーニング:舌や唇の筋力を鍛える練習も効果的です。
当院での取り組み
当院はお子さんから大人まで、噛む力を守るための包括的な治療と予防を行っています。
– 小児歯科での成長段階に応じたケア
– 小児矯正による顎の発育サポート
– 成人へのインビザライン矯正
– 定期的な予防歯科での噛む力チェック
– 失った歯を補うインプラント治療
こうした多方面からのアプローチで、一生自分の歯で噛める喜びをサポートしています。

まとめ
噛む力は単に食べるためのものではなく、全身の健康・脳の働き・姿勢・生活の質にまで影響します。
虫歯や歯周病を予防し、歯並びを整え、失った歯を補うことが「噛む力」を守る秘訣です。
「安城 小児歯科」「新安城 矯正」でお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当院はお子さんから大人の方まで、一人ひとりに合わせた治療と予防で健康な生活をサポートいたします。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長