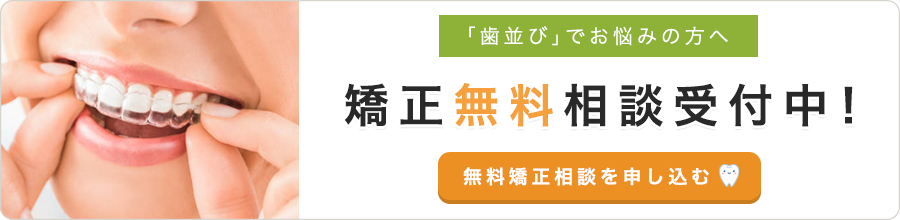こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
診療の現場でよくご相談いただくのが「子どもの歯並びは大丈夫でしょうか?」という質問です。
実は歯並びは単に歯の大きさや生え方だけで決まるものではなく、顎の成長と密接に関係しています。
今回は、顎の成長と歯並びの関係、そして放置した場合のリスクや改善方法について詳しく解説します。
目次
なぜ顎の成長が歯並びに関係するのか?
歯は顎の骨の中に生えるため、顎が小さいと歯がきちんと並ぶスペースが不足します。
その結果、歯が重なって生える叢生(そうせい)や、前歯が前方に出る上顎前突(出っ歯)、反対に下顎が出てしまう反対咬合(受け口)などが起こります。
顎の成長は遺伝的な要素だけでなく、生活習慣や口腔機能にも影響を受けます。口呼吸や指しゃぶり、舌の癖などがあると顎の成長を妨げ、歯並びに悪影響を与えるのです。
顎の成長の大切な時期
顎の成長は一生続くわけではなく、特に乳幼児期から思春期にかけて大きく変化します。
- 3〜6歳:乳歯列が完成し、顎の横幅の成長が活発な時期。
- 6〜12歳:永久歯が生え替わり、顎が前後に成長する重要な時期。
- 12歳以降:成長のピークを迎え、骨格がほぼ固まってくる。
この時期に適切なアプローチを行うことで、顎の成長を正しく導き、歯並びの改善や将来の矯正治療の負担を軽減できます。

顎の成長不足が引き起こす歯並びの問題
顎の成長が不十分だと、以下のような問題が起こりやすくなります。
- 叢生(歯の重なり):歯が並ぶスペースが不足し、ガタガタの歯並びになる。
- 出っ歯:上顎が過度に成長、あるいは下顎の成長不足で前歯が突出する。
- 受け口:下顎の成長が強すぎたり、上顎の成長が不足して反対咬合になる。
- 開咬:前歯が噛み合わず、口呼吸や舌の癖が原因で悪化。
これらは見た目の問題だけでなく、噛む機能や発音、全身の姿勢にも影響を与えます。
家庭でできる顎の成長チェック方法
次のような特徴がある場合は、顎の成長に問題があるサインかもしれません。
- 口を閉じると顎の下に梅干しのようなシワができる
- 寝ているときに口が開いている(口呼吸)
- 前歯で食べ物を噛み切るのが苦手
- 歯並びがガタガタしている
- 下顎が前に出ている、あるいは後退している
1つでも当てはまれば注意が必要です。3つ以上当てはまる場合は、早めに小児歯科や小児矯正の相談をおすすめします。
顎の成長を促すための取り組み
顎の成長は自然に任せるだけでは不十分なこともあります。
当院では、以下のような取り組みを通して顎の健全な発育をサポートしています。
- 口腔機能トレーニング(MFT):舌や唇、頬の筋肉を鍛え、正しい口の使い方を習得。
- 生活習慣改善:口呼吸を鼻呼吸に改善、指しゃぶりの早期卒業。
- 小児矯正:顎の成長を利用して歯列のスペースを確保(小児矯正ページ参照)。
- 予防歯科:定期的に顎や歯列の成長をチェックし、虫歯予防とあわせて管理(予防歯科ページ)。
当院での小児矯正の特徴
当院では小児歯科として、お子さんの成長段階に合わせた矯正を行っています。
最新の3Dスキャナーで顎や歯列を正確に分析し、将来を見据えた治療計画を立てます。
また、思春期以降に必要な場合は、成人矯正やインビザラインへとスムーズに移行できる体制を整えています。
「成長期を逃さないこと」が、最も大切なポイントです。
まとめ
顎の成長は歯並びと密接に関わり、成長不足は叢生や出っ歯、受け口など様々な問題を引き起こします。
早期に正しいアプローチを行うことで、将来の矯正治療の負担を軽減できます。
「安城 小児歯科」「新安城 小児矯正」でお探しの保護者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
お子さんの健やかな成長と美しい歯並びのために、当院が全力でサポートいたします。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長