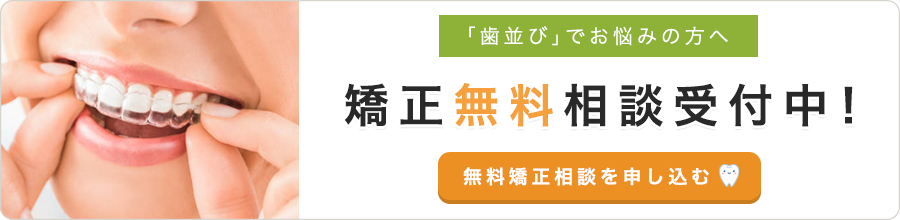こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
今回は、「口臭が気になる!どうすればいい?」についてお話をしていきます。
口臭は、自分ではなかなか気づきにくく、周囲に迷惑をかけてしまう可能性があるため、多くの方にとって大きな悩みの一つです。
実際、歯周病や舌苔(ぜったい)、内科的疾患など、原因はいくつか存在しますが、日頃のケアや専門的な治療によって改善できる可能性があります。
本記事では、口臭の原因や予防方法、歯科医院での対策などをわかりやすく解説し、日常生活の中で役立つ情報をお伝えします。
────────────────────────
【目次】
-
口臭の主な原因とは?
-
歯周病による口臭
-
胃の不調が引き起こす口臭
-
舌苔(ぜったい)の影響
-
口臭予防のための日常ケア
-
口臭が改善しないときの対処法
-
まとめ
────────────────────────
1,口臭の主な原因とは?
口臭にはいくつかの原因が考えられますが、大きく分けると以下の三つが代表的です。
(1) 歯周病などの口腔内トラブル
(2) 胃や消化器系の不調
(3) 舌苔(ぜったい)の付着
たとえば、歯周病菌が繁殖すると嫌なにおいが発生しやすくなります。また、胃の病気や食生活の乱れによって、口から胃のにおいが上がってくる場合があります。さらに、舌の表面に汚れや細菌の死骸が付着することで起こる舌苔も、口臭の大きな原因です。これらは単独で発生することもあれば、複数の要因が重なってにおいが強まることもあります。口臭が複合的に起きるケースも多いので、日頃のセルフケアだけでなく、必要に応じて歯科医院や内科で原因を調べることが大切です。
2,歯周病による口臭
歯周病は、日本人が抱えるお口の悩みの中でも特に多い疾患です。歯周病とは、歯と歯ぐきの境目や歯肉の奥に溜まったプラーク(歯垢)が原因で起こる炎症状態のことで、進行すると歯を支える骨が溶けたり、歯ぐきが下がったりします。歯周病が進行すると、歯肉が腫れる・出血するだけでなく、細菌による独特のにおいも発生しやすくなります。
また、歯周病の怖い点は、進行しても痛みを感じないケースが少なくないことです。「歯ぐきが時々腫れるけれど、なんとなく慣れてしまった」という方も多く、自覚症状が少ないまま口臭を放置してしまう場合があります。歯周病の初期段階であれば、正しいブラッシングや定期的な歯科クリーニングなどで改善が可能です。歯ぐきの腫れや出血が気になった時点で、早めに歯科医院へ相談するのが望ましいでしょう。
3,胃の不調が引き起こす口臭
口臭の原因は口腔内だけにとどまらず、内科的要因から発生するケースもあります。たとえば胃の病気や食習慣の乱れなどで胃液の逆流が起こり、においの原因となることがあります。実は口臭のすべてが歯周病や舌苔だけとは限らないため、歯科医院で口腔内環境を整えても口臭が消えない場合は、内科的な検査を受けることも視野に入れましょう。
特に胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などは、慢性的に胃液が上がってくることで独特の酸っぱいにおいが生じる場合があります。また、長時間空腹状態が続くと唾液の分泌が減り、口腔内が乾きやすくなり、結果として嫌なにおいを発生させることも。口臭対策として定期的な食事や水分補給を行い、口内環境が乾燥しないよう心がけることも大切です。
4,舌苔(ぜったい)の影響
舌苔とは、舌の表面に付着した食べカスや細菌の死骸などの汚れを指します。白っぽい苔のように見えるので「舌苔」と呼ばれますが、これが厚く溜まると口臭が強くなる傾向があります。舌ブラシなどを用いて落とすことで、一時的ににおいを緩和する効果はありますが、やり過ぎは舌の粘膜を傷つけるリスクがあるため、注意が必要です。
最近では、舌専用のハミガキ粉がCMで紹介されるなど、舌苔ケアの方法もさまざまになってきました。一方で、間違ったケアによって舌を傷めてしまい、味覚障害など別の問題につながることもあるので、歯科医師や歯科衛生士に正しい舌ブラシの使用方法を相談することをおすすめします。
5,口臭予防のための日常ケア
(1) 正しいブラッシング方法
歯周病を予防・改善するための第一歩は、歯と歯ぐきの境目を意識した丁寧なブラッシングです。歯ブラシの角度を45度ほどに当て、歯肉の周辺までしっかり磨きましょう。力を入れすぎる必要はありませんが、一定の時間をかけてまんべんなく磨くことが大切です。
(2) 歯間ケアの徹底
歯と歯の間は歯ブラシだけでは汚れが落ちにくいため、デンタルフロスや歯間ブラシを活用して清掃しましょう。歯間部分の汚れが溜まりやすい人ほど口臭が強くなりがちです。
(3) 舌のケア
舌ブラシを使う際は、優しく表面をなでるように行いましょう。ゴシゴシこすりすぎると舌の表面が傷つき、逆に細菌が増えやすくなってしまうこともあります。定期的に歯科医院で舌苔の状態をチェックしてもらうと安心です。
(4) 水分補給
口の乾きは口臭を強める要因です。唾液は口内を清潔に保ち、細菌の繁殖を抑える役割があります。こまめに水分を摂取し、唾液量を保つことを意識しましょう。特に長時間会話をし続ける仕事や、高齢の方は口腔乾燥(ドライマウス)になりやすいので要注意です。
(5) 規則正しい食生活
胃の不調からくる口臭を防ぐためにも、食生活の乱れを見直すことが重要です。規則的に食事を摂ることで胃の負担を減らし、唾液の分泌も促進できます。
口臭が改善しないときの対処法
(1) 歯科医院での検査・治療
歯周病や虫歯などが原因であれば、専門的な処置によって口臭の改善が期待できます。普段の歯みがきだけでは落としきれない歯石やプラークを除去することで、お口の環境を整えられます。
(2) 内科での受診
歯科医院での検査結果に問題がなかった場合、胃や消化器の病気がないか内科を受診してみましょう。特に、胃の不調や逆流性食道炎などが疑われる場合は、専門医による診断と治療が必要になります。
(3) 専門的な口臭外来
通常の歯科検診やクリーニングでは改善が見られないほど、しつこい口臭にお悩みの方は「口臭外来」を設置している医療機関を検討するのも一つの方法です。口臭測定器を使用して科学的に原因を特定し、必要に応じて複数の診療科との連携治療を行う場合もあります。
まとめ
口臭は、歯周病菌や舌苔、内科的疾患など、さまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。自覚しにくい一方で、他人に不快な思いを与えるデリケートな問題でもあります。日頃から正しいブラッシングや舌のケア、水分補給などを心がけ、定期的に歯科医院でプロのチェックを受けることで、口臭を防ぐことができます。万が一、それでも口臭が改善しない場合は、胃腸など別の原因が潜んでいるかもしれません。歯科・内科ともに相談しながら、早期発見・早期治療を行うことで、日常生活の質を向上させましょう。
毎日のケアで清潔なお口を目指し、自分はもちろん周りの方にも不快感を与えない爽やかな息を保つことは、コミュニケーションにおいて大きなメリットとなります。ぜひ、今回ご紹介した内容を参考に、口臭予防に取り組んでみてくださいね。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長