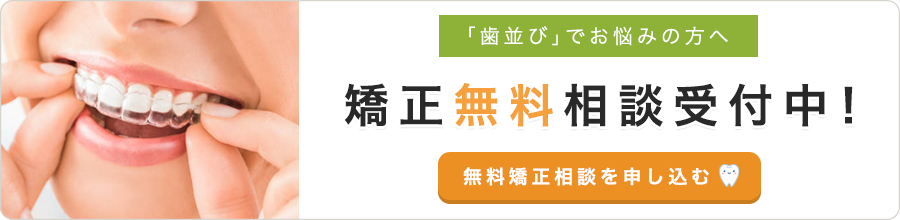こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
今回は、「フロスは使ったほうが良いの?」についてお話をしていきます。
歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れまではなかなか落としきれず、むし歯や歯周病の原因になりやすいといわれています。
そこで、糸状の清掃器具であるフロスを活用することで、歯と歯の間のプラーク(歯垢)をしっかり取り除くことができ、お口の健康を保ちやすくなります。
フロスには糸巻きタイプやホルダータイプなど種類があり、正しい使い方を覚えることで歯ぐきの炎症やむし歯を予防する効果が期待できます。
今回は、フロスを使うメリットや実際の使用方法、頻度などを詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
――――――――――
-
フロスとは何か?
-
フロスを使うメリット
-
フロスの種類と正しい使い方
-
フロスを使う頻度とタイミング
-
フロス選びのポイントと注意点
-
歯ブラシとの使い分けと併用のコツ
-
フロスを始める際によくある質問
-
当院でのフロス指導とサポート
-
まとめ
――――――――――
【1. フロスとは何か?】
フロスとは、糸のように細い清掃器具のことです。一般的には「糸ようじ」と呼ばれることもあります。歯ブラシだけでは毛先が届きにくい、歯と歯の間の汚れをかき出すために使われます。実は歯ブラシだけで取り除けるプラークは、全体の50〜70%程度といわれています。つまり、歯ブラシだけでは十分にお口の中を清掃できず、むし歯や歯周病を引き起こすリスクを減らしきれていないのです。そこで、この歯と歯の間に詰まった食べかすやプラークを除去する役割を担うのがフロスになります。
フロスを使うことで、歯ブラシでは取り切れない場所にアプローチでき、結果的にお口の環境をよりクリーンに保つことができます。特に歯ぐきの境目や歯と歯ぐきの間の隙間は汚れが溜まりやすく、そこにプラークが溜まると歯周病の原因になることがあります。フロスの細い糸でこの部分を丁寧に掃除してあげることで、歯ぐきを健康的に保つことにもつながります。
――――――――――
【2. フロスを使うメリット】
(1) むし歯予防
歯と歯の間は食べかすが溜まりやすく、なおかつ歯ブラシが届きにくい部分です。放置すると、気づかないうちにむし歯が進行している可能性があります。フロスを習慣的に使うことで、歯間のプラークをしっかり取り除き、むし歯予防につなげられます。
(2) 歯周病予防
歯ぐきに炎症が起きて出血しやすくなったり、腫れたりするのが歯周病の初期症状です。進行すると歯を支える骨が溶け出して歯がグラグラし始め、最終的には歯を失うことにもなりかねません。フロスを使って歯ぐきの近くにある汚れを除去することで、歯周病の予防・進行抑制に効果が期待できます。
(3) 口臭の予防
歯と歯の間に溜まった汚れや食べかすは、時間が経つと細菌が増殖し、口臭の原因になります。フロスの使用習慣をつけて清潔を保つことで、気になる口臭の予防にも役立ちます。
――――――――――
【3. フロスの種類と正しい使い方】
フロスには大きく分けて「糸巻きタイプ」と「ホルダータイプ」があります。
● 糸巻きタイプ
細いフロスの糸が巻き付けられており、必要な長さを切り取って使用します。両手の薬指にフロスを巻き取り、親指や人差し指を使って歯の間に糸を通していきます。慣れるまでは少し難しく感じるかもしれませんが、慣れると細かな調整がしやすく、歯ぐきへの負担を減らしながら効率よく汚れを除去できます。
● ホルダータイプ
Y字型やF字型などの持ち手がついているタイプです。糸を手に巻き付ける作業がないので、初心者でも扱いやすいという利点があります。特にお子さまや、ご年配の方、また手先が不器用な方には、ホルダータイプから始めるとストレスなく使いやすいでしょう。
【正しい使い方のポイント】
-
フロスを歯と歯の間にゆっくり挿入する
無理やり押し込むと歯ぐきを傷つける恐れがあるので、軽い力で入れていきます。 -
歯の面に沿わせるように上下に動かす
「のこぎりを引くように」ではなく、歯の面に密着させるようにしてプラークをかき出すイメージです。 -
両隣の歯の面をしっかり清掃する
1か所の歯間でも、左右両側の歯の面をそれぞれ磨きます。 -
使用後はフロスを清潔に保つ
糸巻きタイプの場合は使い回しをせず、毎回新しい部分を使いましょう。ホルダータイプは使い捨てタイプと、糸を交換できるタイプがありますので、清潔さを保つことが大切です。
――――――――――
【4. フロスを使う頻度とタイミング】
一般的には、1日1回のフロス使用が理想的といわれます。特に、寝る前は時間も取りやすく、就寝中は唾液の分泌量が減って細菌が増殖しやすいので、歯間を清潔にしてから眠るのがおすすめです。忙しい日中は歯ブラシのみという方も、就寝前だけはしっかりフロスを使う習慣をつけてみてください。
また、食事内容によっては、歯と歯の間に繊維質の食べ物が詰まったままになっている場合もあります。食後に違和感を覚える場合や、歯の間に明らかな食べかすが詰まっていると感じた場合には、すぐにフロスを使って取り除いておくといいでしょう。
――――――――――
【5. フロス選びのポイントと注意点】
フロスを選ぶ際は、以下の点を考慮してみてください。
(1) フロスの太さや形状
歯間が狭い方は、ワックス付きで滑りの良い薄手のフロスが使いやすいでしょう。逆に歯間に余裕がある方は、少し太めのものを選ぶと汚れをしっかり絡め取れます。
(2) ワックスの有無
ワックス付きのフロスは歯間に通しやすいメリットがある一方、ノンワックスのフロスは繊維が広がって汚れを絡め取りやすい場合があります。自分の歯並びや使いやすさの好みに合わせて選ぶことがポイントです。
(3) 力加減と使用時の痛みに注意
強い力で無理やりフロスを押し込むと歯ぐきを傷つける恐れがあるため、最初はゆっくりとソフトタッチを意識しましょう。もし使用中に痛みや出血が続くようなら、歯科医院で相談することをおすすめします。
――――――――――
【6. 歯ブラシとの使い分けと併用のコツ】
歯ブラシは歯の表面や奥歯の咬合面(かみ合わせ部分)を清掃する上で非常に重要ですが、歯間部に入り込むのは難しい面があります。そのため、歯ブラシとフロスを併用することで、さまざまな角度から汚れを除去でき、結果的にむし歯や歯周病、口臭を予防しやすくなります。
ブラッシングのコツとしては、まずは歯ブラシで全体を丁寧に磨き、その後にフロスを使って歯と歯の間を仕上げるイメージを持つとよいでしょう。さらに、歯間ブラシなども選択肢に入れて、歯並びや歯間の広さに応じて使い分ける方法もあります。特にブリッジや矯正装置を装着している方など、部分的にケアが難しい場所がある場合は、歯間ブラシを組み合わせることでケアがより効果的になるケースも多いです。
――――――――――
【7. フロスを始める際によくある質問】
Q1. フロスを使ったら少し出血しました。大丈夫でしょうか?
A. 初めてフロスを使用した際や、歯ぐきに炎症がある場合は出血することがあります。強くこすりすぎないように注意しながら、数日続けてみてください。もし痛みや出血がずっと続くようであれば、早めに歯科医院で診察を受けることをおすすめします。
Q2. フロスを使うのは毎日でなければいけませんか?
A. 毎日使うことが理想ですが、最初は1~2日に1回でも習慣化できるだけで大きな進歩です。継続することで歯と歯の間がより清潔になり、むし歯や歯周病のリスクを下げられます。
Q3. ホルダータイプと糸巻きタイプ、どちらを使ったほうが良いですか?
A. 一概にどちらが絶対に良いということはありません。初心者やお子さまはホルダータイプの方が手軽に使えることが多いです。慣れてきたら糸巻きタイプに移行してみるのも良いでしょう。それぞれの特徴を踏まえて、自分に合った使いやすいタイプを選んでください。
――――――――――
【8. 当院でのフロス指導とサポート】
当院では、歯磨き指導の一環としてフロスの正しい使い方のレクチャーを行っています。実際に患者さまのお口の状態に合わせて、歯間ブラシやフロスの太さやタイプの選び方もアドバイスさせていただきます。「歯間にフロスが通りにくい」「どうしても出血してしまう」といったお悩みがある方は、一度ご相談いただければ実際に使い方を目の前でご説明することも可能です。特に小さなお子さまの場合は、保護者の方がフロスを使ってみせるだけでも、将来的な口腔環境を大きく左右する良い習慣づくりにつながります。
また、むし歯ができやすい部分や歯石が溜まりやすい箇所などは人それぞれ異なります。定期検診やクリーニングの際にご自身のリスクを確認することで、フロスの使用方法だけでなく、どのくらいの頻度で歯科医院に通院すれば良いかなど、より効果的なケアプランを立てることができるでしょう。
――――――――――
【9. まとめ】
フロスは歯ブラシだけでは行き届かない歯と歯の間の汚れを取り除くための大切なケア用品です。むし歯や歯周病、さらには口臭予防にも効果があり、しっかりと使い続けることで歯の健康を保ちやすくなります。初めは慣れないかもしれませんが、毎日でなくても良いので少しずつ習慣化していくことが大切です。糸巻きタイプやホルダータイプなど、自分に合ったものを選び、正しい方法で使うことで、より効果的に汚れを落とすことができます。
歯と歯の間はむし歯が見つかりづらく、気づいた頃には症状が進行している場合が少なくありません。少しでも「歯間の汚れが気になる」「歯ブラシだけで大丈夫かな?」と思われたら、ぜひフロスを取り入れてみてください。定期検診を受けながら、フロスの使い方や選び方を歯科医師や歯科衛生士に相談することで、より快適かつ確実なケアができるようになります。きれいな歯と健康な歯ぐきを保つために、フロスを上手に活用していきましょう!
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会 名古屋大会 大会長