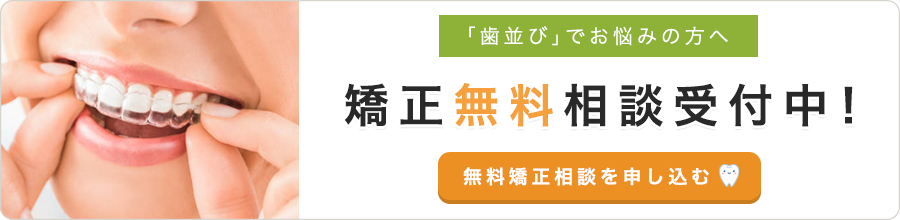こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
今回は、「保険の被せ物の下はむし歯になりやすい?」についてお話をしていきます。
保険診療で装着する被せ物は、比較的費用を抑えられるため多くの方が利用しています。
ところが、その下の歯がむし歯(う蝕)になることがあるのはご存じでしょうか。
被せ物自体は人工物なのでむし歯にはなりませんが、その下にある天然歯との間にはどうしてもわずかな隙間が生まれ、そこにプラークがたまってしまうと「二次カリエス(再度むし歯が発生すること)」を引き起こす可能性があります。
本記事では、保険の被せ物の特徴や、なぜ二次カリエスが起こりやすいのか、さらに予防やケアのポイントについてわかりやすくお伝えいたします。
――――――――――――――――――――
-
保険の被せ物とは?
-
被せ物の下でむし歯が発生しやすい主な理由
-
二次カリエスを防ぐために大切なポイント
-
メタルフリー治療のメリットと注意点
-
保険の被せ物と自費の被せ物の違い
-
長持ちさせるためのケア方法
-
まとめ
――――――――――――――――――――
【1. 保険の被せ物とは?】
保険診療の範囲で作られる被せ物は、金属や硬質レジン(プラスチック)などを用いたものが代表的です。国が定める診療報酬基準に則った治療となるため、費用面では比較的安価に済ませられるのが大きなメリットです。
しかし、保険の被せ物には使用できる素材や作製工程に制限がある場合もあり、必ずしも精密度が高いというわけではありません。
そのため、微小な段差や隙間が生じやすく、長い年月の使用とともにさまざまなトラブルが起こりやすくなります。
――――――――――――――――――――
【2. 被せ物の下でむし歯が発生しやすい主な理由】
(1) 二次カリエスとは?
被せた歯で問題となるのが、すでに治療を終えたはずの歯が再びむし歯になる「二次カリエス」です。被せ物自体は人工物であるため直接むし歯になることはありませんが、その下の天然歯にプラークが蓄積し、むし歯を再発してしまうのです。
(2) 微細な隙間の存在
いくら精密に作製されても、天然歯と被せ物の間には僅かな隙間ができます。時間の経過とともに、噛み合わせの力や接着剤の劣化によりこの隙間が拡大しやすくなります。そこに歯垢や細菌が入り込み、むし歯を引き起こすリスクが高まります。
(3) 接着剤(セメント)の劣化
被せ物と歯を接着しているセメントも、年数が経つごとに劣化します。唾液や熱の影響を受け続けることで接着力が弱まり、結果として歯との密着度が下がり、二次カリエスの原因となる可能性が上がります。
(4) 金属イオンの溶け出し
保険の被せ物には金属が使われていることが多く、金属は唾液や食事などの影響でわずかずつイオンとして溶け出していきます。金属が溶け出すことで素材が薄くなり、または変色や腐食が生じることもあり、そこから細菌が入り込みやすい環境になる場合があります。
――――――――――――――――――――
【3. 二次カリエスを防ぐために大切なポイント】
(1) 定期検診を受ける
治療後も定期的に歯科検診を受けることで、被せ物や隣接する歯の状態をチェックし、早期に問題を発見できます。特に被せ物周辺はむし歯の再発に気づきにくいため、プロの目で見てもらうことが重要です。
(2) 毎日の口腔ケア
歯磨きの際は、被せ物との境目にプラークがたまりやすいことを意識し、細かいところまで丁寧に磨く必要があります。デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助器具も活用し、歯と歯の間や被せ物の周辺をしっかり清掃することが大切です。
(3) フッ素やキシリトールの活用
フッ素入り歯磨き粉やキシリトールガムを利用することで、歯質の強化や細菌の働きを抑制し、むし歯リスクを下げることが期待できます。
――――――――――――――――――――
【4. メタルフリー治療のメリットと注意点】
近年、金属を使用しない「メタルフリー治療」が注目されています。セラミックやジルコニアなどの素材は金属アレルギーのリスクが少なく、自然な見た目や精密な適合度が期待できる点が特徴です。金属が溶け出す心配がほとんどないため、二次カリエスのリスク低減につながる可能性もあります。ただし、素材や技術によっては保険外となるため、費用面では高くなることがあります。また、歯ぎしりや強い噛み合わせ力がある場合には、素材選びや設計に注意が必要です。
――――――――――――――――――――
【5. 保険の被せ物と自費の被せ物の違い】
保険診療で作る被せ物は、国が定めるルールや素材の制限によってコストを抑えられる一方、適合精度や金属アレルギーリスクなどに課題がある場合があります。一方、自費診療(自由診療)の被せ物は、より高品質な素材や先進的な技術を選択しやすいため、適合性が高く審美性にも優れています。しかしながら、自由診療では費用が高額になりがちである点も考慮しなければなりません。
患者さんのライフスタイルやお口の状態、治療に対する考え方、将来にわたるメンテナンスの頻度などを総合的に判断して、保険診療と自費診療のどちらが望ましいかを決定することが大切です。
――――――――――――――――――――
【6. 長持ちさせるためのケア方法】
(1) 正しいブラッシング指導
歯科医院で自分に合ったブラッシングの仕方を教わると、むし歯や歯周病のリスクを大幅に抑えることができます。被せ物は、歯と歯肉の境目や隣り合う歯との間がとくに汚れやすいため、歯磨き粉をつける際はしっかりその部分を意識して磨くと効果的です。
(2) 食生活の改善
砂糖の多い飲食物を頻繁に摂ると、むし歯を促進する細菌が活発化します。また、ダラダラ食べをするほど口の中に糖分が長く滞留してしまい、歯の再石灰化が追いつかなくなるため、二次カリエスのリスクが上がります。食事の時間や糖分摂取のタイミングをコントロールし、水分補給も適切に行うことが大切です。
(3) 定期的なメンテナンス
被せ物の状態は、経年劣化や噛み合わせの変化により少しずつ悪化する可能性があります。歯科医院で定期的にメンテナンスを受けることで、被せ物がしっかり機能しているか、再治療が必要な段階かを早期に判断できます。問題が小さいうちに処置を行うほど、治療の負担は軽減しやすくなります。
――――――――――――――――――――
【7. まとめ】
保険の被せ物は費用面で助かる一方で、長い目で見たときに二次カリエスのリスクを抱えやすい側面があります。金属が溶け出すことや接着剤の劣化によって隙間が生じ、そこに歯垢や細菌がたまってしまうことでむし歯が再発するケースも少なくありません。定期検診や正しいホームケアはもちろん、治療を長持ちさせるためには適切な素材選択やメタルフリー治療の活用も検討してみる価値があります。
一生使う大切な歯を守るには、早期発見・早期治療はもちろんのこと、予防とメンテナンスが欠かせません。保険診療の被せ物でも、適切にケアを行えば十分に長持ちさせることは可能です。ご自身のライフスタイルや健康状態を考慮しながら、歯科医師とじっくり相談してベストな選択をすることで、美味しく食事をしながら歯を大切にしていきましょう。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長