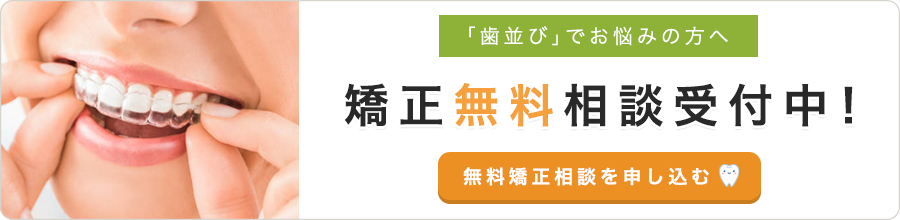こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
今回は、「だらだら食いが引き起こすリスクと対策について」お話をしていきます。
私たちの食生活は、忙しさや生活リズムの変化によって、ついつい「だらだら食い(間食を長時間続ける食べ方)」をしてしまいがちです。
しかし、このだらだら食いは、歯の健康だけでなく身体全体の健康にも大きな影響を与えます。
むし歯の原因になるのはもちろん、胃腸や血流にも負担をかけ、肥満や老化を促進するリスクも高まるのです。
本ブログでは、だらだら食いがもたらす様々なデメリットを詳しく解説するとともに、今から始められる対策や習慣づくりのポイントをご紹介します。
────────────────────────
1.だらだら食いとは?
2.だらだら食いが歯にもたらす影響
3.だらだら食いが身体にもたらす影響
4.だらだら食いを防ぐ食事リズムのポイント
5.お子さまの食事習慣を見直そう
6.日常生活でできる工夫
7.まとめ
────────────────────────
◇1.だらだら食いとは?
「だらだら食い」とは、1日のうちで決まった時間以外にも、何度もこまめに食べ物や甘い飲み物を口にしてしまうことを指します。おやつの時間や食後に少しつまむ程度では済まず、気がつけば常にお菓子やジュースを片手に、口の中に食べ物が入っているような状態をイメージすると分かりやすいでしょう。
現代社会では、お菓子やスナック類、甘い飲み物などが手軽に手に入り、仕事や家事の合間に“ちょっと小腹が空いたから”とつまんでしまうケースが少なくありません。しかし、この習慣が継続すると、歯や体へのダメージが蓄積され、後々大きなトラブルにつながる恐れがあります。
◇2.だらだら食いが歯にもたらす影響
1)むし歯リスクの増加
食事をすると、口の中が酸性に傾きます。これは、食事によって糖質が取り込まれ、むし歯菌が酸を産生するためです。通常、食後しばらくして唾液の働きによる「再石灰化」が起こり、歯が酸から中性寄りの状態に戻ります。しかし、だらだら食いをしていると、口の中が酸性状態からなかなか抜け出せず、長時間歯の表面が溶けやすい(脱灰が進む)状態になります。結果的にむし歯が急速に進行してしまうのです。
2)唾液の緩衝作用を阻害
唾液には、歯の表面を保護するだけでなく、酸性から中性へとバランスを整える「緩衝作用」があります。しかし常に食べ物が口の中に入っていると、唾液の緩衝作用が追いつかないまま、酸性に傾いた状態が続いてしまいます。特に糖分を含む食べ物や飲み物を長時間だらだらと摂取していると、唾液の役割が生かされず、むし歯ができやすい環境を自分で作り出してしまうのです。
3)お子さまのむし歯が深刻化
当院で診察していても、甘いものを一度に食べるお子さまよりも、時間をかけて長い間ちびちび食べるお子さまの方がむし歯の進行度合いが深刻であるケースが目立ちます。むし歯菌にとっては「酸性状態が続く環境」がなにより好都合。つまり短時間集中型の甘いもの摂取よりも、延々と砂糖や糖分を供給されるだらだら食いの方が、はるかに歯にダメージを与えやすいのです。
◇3.だらだら食いが身体にもたらす影響
1)肥満や老化の促進
食べるたびに血糖値が上昇し、エネルギーが血液中に常に豊富な状態が続くと、余ったエネルギーは脂肪細胞に蓄えられてしまいます。これが習慣化すると肥満につながるだけでなく、老化を促進させる要因にもなるのです。特に夜間のだらだら食いは、活動量が少ない分エネルギーを消費しづらく、体重増加を招きやすいので注意が必要です。
2)胃腸への負担と血流の乱れ
胃腸は食べ物が入ると消化活動を行います。だらだら食いによって常に胃腸が休む時間がなくなると、結果的に胃腸が疲れやすくなり、消化吸収にも悪影響が出てきます。さらに、消化のために血液が消化器官に集まりやすく、手足など末端の血流量が低下する恐れがあります。手足の冷えやだるさを感じる方は、こうした食習慣を見直すことも大切です。
3)エネルギー管理の難しさ
「小腹が空いたからつまむ」という行為は、本人は「食事」と認識しづらいため、カロリー計算や栄養バランスを把握しにくいという問題があります。その結果、糖質や脂質の摂りすぎに気づかないまま、肥満やメタボリックシンドロームへと移行してしまうケースも珍しくありません。
◇4.だらだら食いを防ぐ食事リズムのポイント
1)1日3食をしっかり摂る
決まった時間に食事を摂り、間食をできるだけ減らすことが基本です。朝・昼・晩と、しっかりと栄養バランスを考えた食事を摂ることで、だらだら食いしたい欲求を抑えやすくなります。
2)おやつの時間を決める
どうしても間食が必要な場合は、時間を決めて摂るようにしましょう。お子さまの場合は10時や15時など、決めた時間帯におやつを楽しむ習慣を作ると良いでしょう。大人でも、仕事の合間にカフェや休憩をとる時間を決めておけば、時間外にお菓子や甘い飲み物を手に取る回数が減ります。
3)飲み物を見直す
のどが渇いたら水や無糖のお茶で水分を補給することが大切です。甘いジュースやコーヒーに砂糖をたっぷり入れて飲む習慣がついている場合は、少しずつ減らしていきましょう。
◇5.お子さまの食事習慣を見直そう
1)おやつは「4食目」ではなく補助食と捉える
子どもにとっておやつは、栄養補給や楽しみの一つですが、ダラダラと長時間食べ続けてしまうとむし歯だけでなく食欲の乱れにもつながります。朝昼晩としっかり食事を摂るのを前提に、おやつは基本的に10時と15時など時間を決めて提供すると良いでしょう。
2)保護者も一緒にルールを守る
子どもの食習慣は大人の姿をよく見て学びます。保護者自身がだらだら食いをしていると、その姿を見て子どもも同じ習慣を身に付けてしまう可能性が高いです。大人も含めて家族全体でルールを作り、守るように心がけましょう。
◇6.日常生活でできる工夫
1)しっかり噛んで食べる
食べるスピードが速いと、満腹感を得る前に食べ過ぎてしまいます。よく噛むことで唾液の分泌が増え、歯の表面を保護するだけでなく消化吸収にも良い影響を与えます。よく噛むことで「ちゃんと食べた」という満足感が得られ、間食を減らすことにもつながります。
2)食事の時間を楽しむ
忙しいと「とりあえず口に入れるだけ」の食事になりがちですが、なるべく食卓につき、食べるときは食べることに集中しましょう。味わいながら食べることで、心身ともに満たされ、食後に間食を探してしまうクセを減らすことができます。
3)気軽に専門家へ相談
歯科医院ではむし歯の治療だけでなく、食生活やだらだら食いの改善方法などもアドバイスしています。生活習慣の見直しで分からない点があれば、ぜひ歯科医や歯科衛生士に相談してみてください。

◇7.まとめ
だらだら食いは、むし歯のリスクを高めるだけでなく、肥満や老化、胃腸への負担など身体全体に様々な問題を引き起こします。まずは1日3食の食事をきちんととり、おやつの時間を決めることから始めましょう。特にお子さまの食事習慣は早めに整えてあげるほど、将来のむし歯や生活習慣病のリスクを下げられます。
「少し小腹が空いたから」「仕事や勉強の合間に何かを食べていないと落ち着かない」という方は、一度ご自分の食生活を振り返ってみてください。無意識に行っているだらだら食いを減らす工夫をするだけで、歯や体の健康にプラスの効果をもたらすことは間違いありません。
もしも食事や歯についてのお悩みがありましたら、遠慮なくご相談ください。ご自身の歯で美味しく食事を楽しむためにも、日頃から適切な食事リズムを守って、歯と体の健康を守っていきましょう。
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長