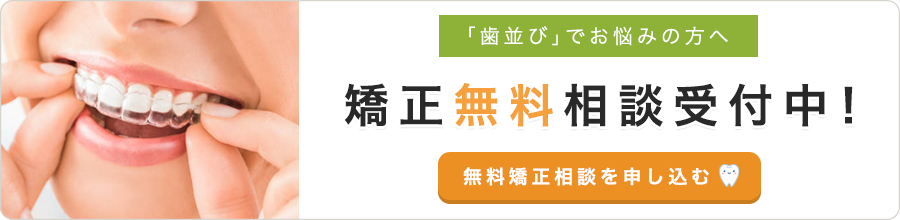こんにちは!安城の歯医者、安城ひがしやま歯科こども矯正歯科、院長の神谷明光です。
歯科医院に行った際に「歯石(しせき)がたまっていますね」と言われた経験はありませんか?
歯石は、歯ブラシでは取り除けないため、いざ診察で指摘されると驚かれる方も少なくありません。歯石は放置しておくと歯周病を急速に進行させるリスクが高く、口腔内環境の悪化を招く原因の一つです。そこで今回は、歯石がどのように形成されるのか、そして歯石の種類や除去の重要性について詳しくご説明していきます。
本記事では、歯石ができるプロセスや歯石を放置するリスク、歯石除去の方法について解説し、さらに歯石がつきにくいお口の環境を整えるための日常ケアのポイントについてもご紹介します。
「歯石は歯を安定させるから取らないほうがいいの?」といった誤解をされている方もいらっしゃいますが、そのままにしておくデメリットのほうがはるかに大きいのです。ぜひこの機会に歯石の正しい知識を身につけ、健やかな口腔環境づくりに役立てていただければ幸いです。
定期的な歯科受診が、生涯を通じた歯の健康を守る鍵となります。
それでは、以下の目次に沿って歯石について記載していきます。
2.目次
- 歯石とは何か?
- プラークから歯石になるまでの流れ
- 歯石の種類(歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石)
- 歯石を放置するリスク
- 歯石除去の方法とポイント
- 当院での歯石除去プロセス
- 歯石を溜めないための日常ケア
- まとめ
1. 歯石とは何か?
歯石とは、歯の表面に付着したプラーク(歯垢)が、唾液などに含まれるミネラル成分によって硬化し、石のようになったものを指します。私たちが日々歯磨きをしているのは、主にプラークを除去するためです。しかし、ブラッシングが不十分だったり、歯と歯の隙間に汚れが溜まったままだったりすると、そこに唾液中のカルシウムやリンなどが沈着していき、どんどん硬くなります。これが歯石です。
一度歯石がついてしまうと、通常の歯ブラシでは除去できません。専門的な器具や超音波スケーラーなどを用いて歯科医院でクリーニングする必要があります。放置しておくと口臭や歯周病の悪化を招くため、定期的に歯石の状態をチェックし、必要に応じて除去することが重要です。
2. プラークから歯石になるまでの流れ
歯石は、いきなりできるわけではありません。その前段階には必ずプラークの蓄積があります。プラークは細菌の塊であり、歯の表面に粘着性の膜を形成します。食後の磨き残しや不十分な歯磨きによってプラークが溜まると、やがて唾液中のカルシウムやリンがその中に沈着し、徐々に硬化していきます。これが歯石となるのです。
- ステップ1:プラークの蓄積
食べかすや磨き残しがあると、菌が増殖してプラークが形成されます。 - ステップ2:唾液中のミネラル沈着
プラークに唾液の成分(カルシウムやリンなど)が沈着すると次第に固まりはじめます。 - ステップ3:歯石の完成
時間が経つほどに固まりが強固になり、歯ブラシでは除去できなくなるほど硬くなります。
このように、歯石は私たちがいかに早期の段階でプラークを除去できるかがカギとなります。毎日のケアを徹底することで、歯石の形成を大幅に抑えることが可能です。
3. 歯石の種類(歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石)
歯石は大きく分けると歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石の2種類があります。
- 歯肉縁上歯石
- 歯ぐきより上の部分(歯肉縁上)に形成される歯石です。
- 唾液中の成分が由来するため、色は灰白色や黄白色が多いです。
- 唾液腺の開口部、特に上下の前歯周辺にできやすい傾向があります。
- 形成速度は比較的速いものの、歯面への接着力は歯肉縁下歯石より弱いため、除去もしやすいとされています(ただし、歯ブラシだけで取れるわけではありません)。
- 歯肉縁下歯石
- 歯周ポケット内(歯肉縁下)に形成される歯石です。
- 歯ぐきの中の感染組織からの浸出液や血液が混ざっているため、色が黒褐色になるのが特徴です。
- 形成速度はゆっくりですが、密度が高く歯面への接着力も強いため、除去には専門の技術が必要です。
- 歯肉の奥深くに入り込んでいることも多く、日常のブラッシングでは届きにくいため、知らないうちに増殖してしまう場合があります。
歯石の成分は、無機質(リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸マグネシウムなど)と有機質(死滅した菌、剥がれた上皮細胞、白血球など)から構成されます。歯肉縁上歯石では16~51%、歯肉縁下歯石では32~78%が無機質とされ、残りを有機質が占めています。特に歯肉縁下歯石は赤血球なども含まれているため、黒や茶色に見え、より硬くこびりつきやすいのが特徴です。
4. 歯石を放置するリスク
歯石を放置すると、さまざまなリスクが生じます。よく「歯石は歯の揺れを抑えるから取らないほうがいいのでは?」という誤解がありますが、歯石がついたままの状態はむしろ歯を失う原因ともなりかねません。その主な理由は以下の通りです。
- 歯周病の進行
歯石の表面は細菌が付着しやすいため、歯周病が急速に進行する恐れがあります。歯ぐきが炎症を起こす歯肉炎から始まり、歯を支える骨が溶ける歯周炎へと発展してしまうと、歯の寿命が短くなります。 - 口臭の原因
歯石や歯石周辺のプラークに含まれる細菌によって口臭が引き起こされるケースが多く、放置するとますます口臭が強くなってしまいます。 - 見た目の問題
歯石は茶色や黒色を帯びることがあり、口を開けた時に目立つようになると、人前での会話や笑顔に自信が持てなくなることもあります。 - むし歯リスクの増大
歯石そのものがむし歯を直接引き起こすわけではありませんが、歯石の周辺にはプラークが残りやすくなるため、むし歯リスクが高まります。
以上のように、歯石を放置すると総合的にお口の健康が損なわれてしまいます。たとえ歯がぐらつきにくくなるように感じても、それは一時的な感覚であり、根本的な健康リスクを見逃してしまうことになるのです。
5. 歯石除去の方法とポイント
歯石除去は、歯科医院で行う専門的なクリーニング(スケーリングとルートプレーニング)が基本です。スケーリングでは専用の器具や超音波スケーラーを使って歯石を除去し、ルートプレーニングでは歯の根面(歯肉の下に隠れている部分)の表面を滑らかに整えます。歯石をしっかり取るだけでなく、再び歯石がつきにくい環境をつくるためにも必要な工程です。
- スケーリング(歯石取り)
歯肉縁上および歯肉縁下に付着した歯石を、超音波スケーラーやハンドスケーラーで削り落とします。 - ルートプレーニング
歯根の表面を滑らかにし、歯石やプラークが再付着しにくい状態に整えます。 - ポリッシング
仕上げに、研磨剤を用いて歯の表面を磨き、ツルツルの状態にします。ステイン(着色汚れ)や微細な凸凹を滑らかにすることで、汚れの再付着を防ぎます。
歯石除去の際は、歯肉に炎症がある場合などは多少痛みを感じることがありますが、回を分けて丁寧に処置を進めることで負担を軽減できます。また、定期的に来院していただくことで、大きく歯石がたまる前に取り除くことができ、処置もより短時間・低負担になります。

6. 当院での歯石除去プロセス
当院では、以下の流れで歯石除去を進めています。
- 問診・検査
まずは患者様のお悩みや症状をヒアリングし、歯周ポケットの深さや歯石の付着状態をチェックします。 - 歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)
上述の方法で、歯肉縁上・歯肉縁下にこびりついた歯石を除去していきます。必要に応じて麻酔を行い、患者様の負担を最小限に抑えます。 - ブラッシング指導
歯石除去後は、患者様一人ひとりの口腔内環境に合わせた正しい歯磨き方法をアドバイスします。歯ブラシの当て方や動かし方だけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシの使い方なども細かくご説明します。 - 定期検診のご案内
お口の中は半年も経つと、再び歯石が少しずつたまってしまうことが多いです。当院では、一定期間が空いて来院された方には、原則として歯石除去から治療を行うようにしています。定期的なチェックを受けることで、歯周病やむし歯などの早期発見・早期治療が可能になります。
7. 歯石を溜めないための日常ケア
歯石ができにくい環境を整えるには、日々のセルフケアが欠かせません。以下のポイントを意識してみてください。
- 正しいブラッシング習慣
- 食後、できるだけ早めに歯磨きを行うことでプラーク形成を抑えます。
- 歯ブラシは毛先が広がっていないものを使用し、1~3か月を目安に交換しましょう。
- 歯と歯ぐきの境目を意識し、歯ブラシの毛先がしっかり当たるように45度の角度で優しく磨きます。
- デンタルフロス・歯間ブラシの活用
- 歯と歯の間は歯ブラシだけでは磨き残しが多くなりがちです。
- デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、プラークの除去率を高めましょう。
- 食生活の見直し
- 甘いものや粘着性のある食べ物(キャラメルやグミなど)は、プラークの原因となる菌の栄養源になりやすいです。
- よく噛むことで唾液の分泌を促し、口腔内の自浄作用を高めることも大切です。
- 定期的な歯科受診
- プラークは歯石になる前に取り除くのが一番です。
- 半年~1年に1回程度は定期検診を受け、専門的なクリーニングを行うことで歯石の蓄積や歯周病の進行を防ぎます。
まとめ
歯石は単に「歯磨きをサボった結果つくもの」というイメージを持たれがちですが、実際は誰のお口の中でも少なからず形成される可能性があります。一度固まると、歯ブラシでは除去できなくなるため、定期的に歯科医院でチェックし、必要に応じて専門的なスケーリングとルートプレーニングを受けることが重要です。
「歯石が歯を支えているから、取らないでほしい」という考え方は誤解であり、歯石を温床にして細菌が繁殖すれば、歯周病が進行し、むしろ歯を失うリスクを高めてしまいます。歯肉や歯を健康に保つには、歯石ができにくい環境を整え、万が一できてしまったら早めに除去することが大切なのです。
当院では、歯石除去をはじめとする口腔ケア全般のアドバイスと定期的なメンテナンスを行っています。半年ほど経つと、歯石やプラークはどうしても少しずつ蓄積してしまいますので、歯周病やむし歯のリスクを軽減するためにも、ぜひ定期検診をご利用ください。正しい知識と習慣を身につけることで、あなたのお口の健康を長く守っていきましょう。
—
安城ひがしやま歯科こども矯正歯科
院長 神谷明光
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医
第40回日本ティップエッジ矯正研究会
名古屋大会 大会長